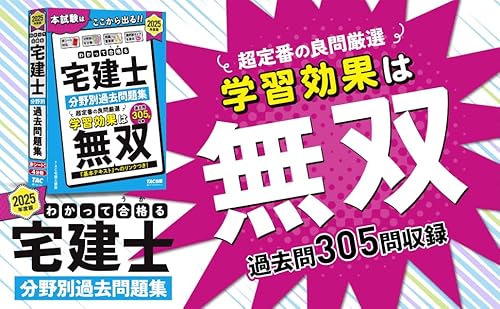令和6年の宅地建物取引士試験に合格したので、その過程と勉強方法を記しておきます。
ワタシのやり方が正解だとは思いません。置かれた環境や条件は人それぞれなので、正解の方法も人の数だけあるんだと思います。
ここに記したことが多くの人の役には立つことはないでしょうが、いつか誰か一人の役にでも立ててもらえるのであればとの思いで記させていただきます。
記事の前半で勉強の過程を、後半で勉強方法をまとめています。必要なければ前半は読み飛ばして下さい。
本題に入る前にワタシのスペックです。
特別何かに秀でてるわけでもなく特別何かを得意としているわけでもない、普通のオッサンです。
年齢: 54歳(受験時)
学歴: 高卒(都立普通科)
得意科目: 国語・地理歴史
苦手科目: 数学・物理化学
不動産業界歴: 皆無
職歴: 販売・サービス・WEB製作・肉体労働
文頭まとめ
ダラダラと長い文章になってしまったので文頭で簡略にまとめておきます。
- 一問一答を分野別に徹底的に解く(~8月まで)
- 年度別に過去問を解いて理解度を確認(9月)
- 各種模試・予想模試を解く(9月後半~直前)
とにかく過去問を一問一答形式で分野別に解いていくことが重要。繰り返し解いていくことで理解度が深まるし、頻出の論点も把握できます。
学習は宅建業法から始めます。宅建試験で最も大きなウェイトを占めるのが宅建業法です。業法だけで20問出るんですから、業法を完璧にしておけば20点は取れるんですよ。
最も難しいとされる権利関係は、出題頻度が高い+丸暗記でなんとかなる「賃貸借」「借地借家法」「区分所有法」「物権変動」「相続」「不動産登記法」あたりを重点的に。
7~8月頃の無料模試はスルー、この時期に模試を受けて一喜一憂する必要は無いです。無料模試を解くなら本番直前の実力把握と苦手把握としてチャレンジ。
繰り返しますが、基礎的な知識が身についていない時期に模試を受けて一喜一憂するのは馬鹿らしいです。そんな暇があったら1つでも多く過去問を解きましょう。
直前期になったら宅建講師の方々がネットで配布する無料模試と、予備校が直前として出版する予想模試(書籍)を解いて現時点での理解度や弱点を確認します。
模試の結果に一喜一憂するのはこの時期になってからで遅くは無いです。
無料模試は難易度別に過去問を改訂したような問題、直前予想模試(書籍)は過去問を難しくしたような初見の問題を解けるので、お金と時間に余裕がある範囲で出来るだけ多く解いておくといいです。
学習過程
学習期間 2024年6月1日~2024年10月20日
学習時間 約380時間
2024年6月 学習の始め
6月1日 勉強を始めるとっかかり
5月末に行われたFP2級試験から1週間後。
「次は宅建を受けてみよう!」と漠然と思い立ちますが、そもそも「宅建ってなに?」というくらい知識不足でした。
まずは宅建試験とはどういう内容なのかを把握するために入門的な参考書を一冊購入しました。
宅建試験のテキスト(教科書)はとても分厚くて、800~1000ページくらいのものが一般的です。いきなりそんなのを購入しても、せっかくのやる気が削がれる結果になってしまいます。
「これだけ!まんが宅建士」は本編が約300ページ、しかもマンガですので文字とイラストだけのテキストよりも遙かに読みやすいです。
ページ数が少ないため宅建試験で出題される内容の全てを網羅しているわけではありませんが、学習の基礎となる基本的な知識はあらかた載っています。
後に分厚いテキストも購入しましたがほとんど手を付けることはありませんでした。それはこのマンガのテキストとWEBから得られる情報だけで十分に学習できるからです。
勉強のとっかかりとして購入しましたが、試験直前の最後の最後まで使える本でした。この本から始めていなければ途中で投げ出していたかもしれません。
どんな資格試験に於いても共通ですが、まず最初に「自分がこれからどのようなことを勉強するのか?」を把握することがとても重要だと思っています。出題される分野だったり範囲だったり。
そのために、大雑把でもいいので「これだけ!まんが宅建士」のような読みやすくて頭に入ってきやすい書籍を一読して、これから勉強する内容とその流れをイメージできるようにしておくとその後の学習が捗ります。
6月6日 過去問を解いてみる
一週間弱の空いてる時間を使って「これだけ!まんが宅建士」を一通り読み終えました。
流し読みしただけですのでこの時点で何かを理解しているわけではありません。
ワタシがそもそも「読んで覚える」タイプの人間ではなくて実践しないと覚えられないタイプの人間なんです。
なので過去問を解きながら覚えることにしました。
宅建試験では過去に出題された問題が公開されています。
公式サイトでは昭和63年の試験まで遡って公開されていますが、さすがにそこまで古い問題を解いていくのはやり過ぎ感が否めませんし、時間もそれほどありません。
というわけで、今回も過去問道場さんにお世話になることに。

ちなみに、「過去問道場で過去問を解きながら覚える」という勉強法は第二種電気工事士試験やFP2・3級の試験のときも通用したことから個人的に絶大な信頼を置いている勉強法です。
ただ、出題の多くが過去問の焼き直しである電気工事士・FPの試験に対して、宅建士の試験は過去問では出たことがない論点も出題されるのが異なるところ。
とはいえ、過去問を完璧にしておいて損することはナニ一つないので、まずは過去問から取り組むことをお薦めします。
手始めに過去問道場さんの一問一答モードで「宅建業法」の分野を最初から解いていきました。
当然ですが分からない問題がほとんどです、その分からない問題を「これだけ!まんが宅建士」を読みながら答えていきます。「これだけ!まんが宅建士」を読んでも間違えてしまう問題、「これだけ!まんが宅建士」には掲載されていない知識が問われる問題もたくさんあります。それらの問題内容は別にメモしておいて(過去問道場の機能でチェックを入れることも可能です)、一通り終わったあとに個別に調べていきました。
過去問道場さんでは平成12年の試験問題まで遡って、過去25年分の過去問を学習できます。
過去問道場さんでは「過去問道場」と「一問一答道場」の2つのモード?を選んで学習できます
「過去問道場」とは文字通り、各年度の過去問を解いていくモードです。分野別や難易度別など出題の仕方を柔軟にカスタマイズできるので様々な勉強法に対応しています。
「一問一答道場」では、各問題の選択肢ごとに正誤(○×)を回答していくモードです。
出題例)
過去問道場
問)次のうちから正しいものを選べ
1, 猫は十二支に含まれる
2, 犬は十二支に含まれる
3,兎は十二支に含まれる
4,馬は十二支に含まれる一問一答道場
問)正しければ○、間違っていれば×で答えよ
1, 猫は十二支に含まれる
問)正しければ○、間違っていれば×で答えよ
1,馬は十二支に含まれる
問)正しければ○、間違っていれば×で答えよ
1,兎は十二支に含まれる
問)正しければ○、間違っていれば×で答えよ
1, 犬は十二支に含まれる
こんな感じで、「過去問道場」では4択の中から正解を選びますが、「一問一答道場」では選択肢ごとに正誤を回答するわけです。
詳しいことは後述しますが、過去問を使って学習する際に最も大事なことは選択肢ごとに「一問一答」で正誤を考えていくことだと思っています。
4択から正解を選ぶだけでは繰り返し解くごとに答えを覚えてしまいますので。
2024年7月~8月 ひたすら過去問を解きまくる
7月~8月の2ヶ月間も6月と同じで過去問を一問一答形式で解いていきました。
宅建試験はいくつかの分野に分かれていますが、勉強の順番としては
- 宅建業法
- 法令上の制限
- 税・その他
- 権利関係
- 五問免除
という順番で進めていきました。
8月の終わりくらいまでに3の「税・その他」までを終わらせるくらいのペース配分で、9月から権利関係に取り組みました。
5問免除は試験直前に丸暗記。
2024年9月 過去問を4択で解き始める
未学習であった権利関係分野の学習を始めると同時に、ここまでずっと「一問一答」形式で解いてきた過去問を本来の出題形式である4択形式で解き始めました。
一問一答形式で選択肢ごとの正誤を回答できるようになっていれば4択形式でも問題なく解けるようになっているはず。
2024年10月 模試を解いて弱点の洗い出し・克服
10月からは無料で提供されている模試を解きました。
ここで大事なのは「過去問ベースの模試」を受験することです。
過去問ベースの模試は文字通り過去問からの出題になっていますので過去問学習の延長として受験できます。
模試の結果から自分の弱点を洗い出せたら、試験日まで弱点を克服するための勉強を続けました。
勉強法、やったこと・やらなかったこと
やったこと
過去問道場
勉強の過程でも書きましたが、ワタシの勉強のほとんどは過去問道場で過去問を解くことでした。ワタシが合格できた要因の8割は過去問道場さんのおかげです。
宅建の学習において過去問学習はとても大事です。
その過去問学習を効率よく行うにために過去問道場さんは欠かせないツールだと思います。
試験日当日、過去問道場さんで表示されたワタシの学習データは以下の通りです。





過去問道場を使って学習する上で大事なのは、基礎固めの段階では必ず「一問一答」形式で学習することです。
宅建の問題や選択肢では独特な言い回しが頻出されます。問題を解くためには読解力が試されるんです。
各選択肢を一問一答形式で解いていくことで問題を読む回数が4倍に増えます(実際にやってみれば分かる)
問題読む機会が4倍に増えればそれだけ宅建の出題文に慣れることが出来ます。
宅建試験では「問題分でナニが問われているのか?」を理解することから始めなければいけないわけです。そのためにも「一問一答」形式での学習が最適です。
Youtube動画を見る
知識のない状態で過去問を解いても早い段階で必ず躓きます。
躓いたところは何らかの方法で学習するのですが、その学習方法としてYoutube動画を利用しました。
数ある資格試験の中でも宅建試験は群を抜いて人気のある試験です。なので宅建試験で収入を得ようとする企業・個人もたくさん参入しています。
そういった企業・個人が宅建試験に向けた学習動画をYoutubeにアップしてくれています。
Youtube講師の方々にもそれぞれ個性がありますし、個人的に合う合わないがあると思いますので自分に合ったチャンネルを見つけると学習効果が高まると思います。
ワタシがお世話になったYoutubeチャンネルはこちら
分野別過去問集
過去問道場さんで過去24年26回分の過去問を解いているうちに、過去に頻出の論点や定期的に出題される論点があることに気がつきます。
ですが大量にある過去問の中からそれらを分析しまとめるのは個人レベルでは難しいし、そんな時間もない。
ということで、分野別の過去問題集を購入しました。
過去問を解くだけなら過去問道場で十分ですが、数ある過去問の中から頻出されてる良問をまとめた問題集を解くことで学習効率が上がります。
また、この問題集では過去問道場には収録されていないもっと古い過去問からも良問が掲載されています。
宅建の学習をするにあたって大事なのは「分野別に順番に学習する」ということです。
そして過去問を解くにあたっても「分野別に解く」ということが重要になります。
過去問ベースの模試
時期は10月に入ってから。試験前の実力測定の意味で受験しています。
試験直前期になると宅建講師の方々が無料の模試を配布されます。それらの無料模試を解いて実力判定しました。
宅建みやざき塾模試
- FIRE
- TRAP
- GIFT
- IMPORTANT
吉野塾
- フリー模試 Green
学習環境の整備
PCを使った自営業であるワタシの場合はデスクトップパソコン+32インチモニタという環境があるのでこれがメインの学習環境です。大きな解像度の大きな画面は快適なのですが、持ち運びが出来ません。
そこで中古のWindowsタブレットPC、Surface Goを追加しました。10インチの折りたたみキーボード付きなので持ち運んで使えます。
加えて、普段使っているiPhoneにも学習用のアプリをインストールして移動中の僅かな隙間時間でも学習できるようにしました。
やらなかったこと
テキスト丸暗記
学習にはインプットとアウトプットが必要ですが、インプットを効率よく行うという観点からテキストを丸暗記することはしませんでした。
例えば新しくテレビを買ったとします。最近のテレビはサブスク動画を見られたりしてとても多機能です。
で、その新しいテレビの使い方を覚えようとした場合、以下のどちらの方法がより早く使い方を覚えられるでしょうか?
1,分厚い取扱説明書を最初から最後まで一通り読んで覚える
2,リモコン片手に操作しながら覚える
恐らくですが、2の方法で覚える人の方が多いのではないかと思います。
宅建の勉強も同じで、テキストを丸暗記するよりも過去問を解きながら覚えた方が効率よく勉強できると思います。
そもそもワタシの場合テキストと呼べる書籍類は、前述した「これだけ!まんが宅建士」しか使っていません。
テキストへの書き込み・付箋
そもそもテキストを買っていないので物理的に出来ないわけですが、個人的に「書いて覚える」タイプの人間ではないのです。なのでテキストがあっても書き込んだり付箋を貼ったりはしません。
その代わり、パソコンやスマホ・タブレットでメモを作っていつでも見返せるようにしていました。
Google Keep や iCloud メモ、Microsoft One Note といった異なるOS間で利用できるクラウドを使ったメモアプリはとても重宝しました。
早い段階での実力判定・オリジナル模試
7月頃になるとLECやTACといった資格学校が実力判定のための模試を公開し始めます。
7月や8月といった早い段階での実力判定が悪いとは言いませんが、この時点での結果に右往左往する必要なんてないんです。
ましてや模試で出題される問題は資格学校が勝手に考えた問題です。過去問で問われたことのない論点も混ざっていたりします。本当に実力判定が出来るのか甚だ疑問です。
最終的な目標は10月の第3日曜日の本試験で合格点を採ることです。
なのに、この段階での模試の結果に一喜一憂する受験生が非常に多いように見受けられます。
Youtube動画の下りでも前述しましたが、宅建試験は資格学校や宅建講師がお金儲けが出来る一大イベントなんです。受験生の不安を煽れば教材が売れるんです。
SNSへの依存
勉強の記録を残したり、同じように勉強をしている人と繋がったり、ワタシもモチベーション維持のためにSNSを使いましたのであまり大きなことはいえないのですが。
- 付箋がビッシリ貼られたテキストを写真に撮ってUPしてみたり
- お洒落なカフェで勉強している自分の姿をタイムラプス動画で撮影してみたり
要ります?その自己顕示。
カラフルな付箋を貼るのは構いませんし、お洒落なカフェで勉強するのも構いませんが、それを写真に撮って編集してSNSにアップしてる時間があるならその間に過去問2~3問解けますよ。
SNSで「勉強してます」アピールをすることが目的なのでは?という人もたくさんいます。それでは本末転倒なので気をつけました。
受験~合格して思ったこと
過去問を解きまくるメリット
宅建試験で出題される問題文は分かりにくいことが多いです。理解しづらいと言った方がいいのでしょうか。
特に登場人物が2人3人と出てくる問題では、ある問題では「賃貸人A、賃借人B」だと思ったら、ある問題では「賃借人A、賃貸人B」とA・Bで立場が入れ替わったりします。
過去問を繰り返し解いていくとこうした問題に引っかかって、演習で不正解になります。その度に思うんです
「ちゃんと問題文を読まなかった!読んでれば正解できたのに!」
と。
この経験はとても大事です。過去問の演習だから「ちゃんと読んでれば正解できた!」と言い訳できますが、本番試験ではそんな言い訳は慰めにもなりません。
問題の読み間違えという凡ミスで1点を落として本番試験が不合格だったとしたら?
1年後の試験まで悔やみ続けることになるんです。
過去問を解きまくる過程で何度もこうしたミスを繰り返すと思います。何度も何度も繰り返し、その都度反省することで少しずつミスの頻度が減っていきます。
かく言うワタシも本番試験で問題を流し読みして1問落としました。
幸いにも合格できましたが、「よく読んでればもう1問正解できていたのに!」との後悔は残ります。
解答用紙の右半分は全問正解する意気込みで
解答用のマークシートは左半分問が1~問25、右半分が問26~問50となっています。
このうちの右半分に割り当てられているのは宅建業法と5問免除科目です。
この宅建業法と5問免除科目は比較的点を取りやすい分野とされていて、多くの受験者がこの25問で点を稼ぎます。
宅建試験は受験者の上位15~18%が合格する相対評価の試験です。他の受験者が正解するであろう問題は絶対に落とせません。
直近の合格点を見ると
2024年試験、37点
2023年試験、36点
2022年試験、36点
となっています。
右半分の25問を全問正解できればそれだけで25点稼げますので、難しいとされる左半分で10問落としても40点取れます。
実際に右半分の25問で満点取れるかは出題の難易度によっても変わると思いますが(ワタシも2問落としました)、満点取る勢いで臨まないと良い結果はでないと思います。
最も出題数が多い宅建業法は早い段階で完璧に覚えておくのが大事です。誰もが得点源とする宅建業法で自分だけ点数を落としていては合格できません。
試験慣れが有利に働いた
2022年の秋から2024年秋にかけて、宅建を含めて10個以上の資格試験を受験してきました。
不動産業界の試験は宅建が初めてで、他はFPだとか第二種電気工事士だとか家電アドバイザーなど異なる様々な業界の資格でしたが、資格試験の勉強方法としてどの試験でも共通することがいくつかあります。
そういった共通の勉強法で身を持って覚えていたことが大変有利に働いたと感じています。
当て勘
これまでたくさんの資格試験を受験してきた過程で「当て勘」を養うことが出来ました。
資格試験ではよく「当て勘」といった言葉が用いられます。当て勘とは霊感とか第六感とかの偶然性に頼ったものではなく、経験則から導き出される「勘」のことです。
例えば
「すべて」「いかなる場合でも」「誰でも」等のワードが入った選択肢は高確率で間違い!
これは有名な「当て勘」の知識です。選択肢の中にこれらの文言が入っていたらまず間違っていることを疑うわけです。
他にも
- ~である
- ~である
- ~でない
- ~である
という4択がでたらまずは3を疑うことから始めてみるのも当て勘です。
他にも色々な当て勘があるようですが、様々な資格試験を受験しているとその学習の過程で当て勘が養われていきます。
令和6年の宅建試験でも過去の出題されたことがない論点がいくつか出題されましたが、当て勘で正解することが出来ました。
人と比べない・ペースを乱さない
30万人が出願する大規模な試験のため、SNSでも多くの人が宅建試験の学習過程をポストしています。
そういった人々の学習の進み方を見るとどうしても自分と比較してしまいがちですが、学習に費やせる時間や環境は人それぞれです。
試験直前期で全く間に合っていないならともかく、夏くらいの時点で差が付けられていても残りの3ヶ月で十分に取り返せます。
前述したように、0円模試などの結果でX(旧Twitter)のタイムラインが賑わい出すのも夏頃からです。
ですが、この時期の模試に一喜一憂する必要はありません。資格学校の思惑に乗る必要はないんです。
高得点に喜んだり、悪い点数に凹んでいる時間はもったいないです。そんな時間があったら過去問で出題された論点を丁寧に理解していきましょう。
過去問で出題された論点は今年の問題でも出題されるかもしれませんが、模試の問題はあくまでも模試の問題です。模試の問題が丸ごと本試験で出題されるわけではないのですから。
前述しましたが、人気資格である宅建試験は結構な規模のビジネスなんです。受験生の不安を煽れば教材が売れてお金が稼げます。
ですが、教材を増やしたからといって学習効果が上がるとは限りません。むしろ混乱に繋がりかねません。
試験まで半年程度あるなら別ですが、8月9月の直前期に新たな教材に手をつけるのは一種のギャンブルです。
過去問の取り組み方
一問一答で解く
宅建に限らず過去問が公開されている資格試験でよく議論されていることに「過去問だけで合格できるか?
というのがあります。
過去問だけで合格できる?と問われたら答えは「イエス」です。
過去問だけでは合格できない?と問われても答えは「イエス」です。
どういうことかというと、例えばこの問題
平成23年(2011年)問50
建築物の構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1 ラーメン構造は、柱とはりを組み合わせた直方体で構成する骨組である。
2 トラス式構造は、細長い部材を三角形に組み合わせた構成の構造である。
3 アーチ式構造は、スポーツ施設のような大空間を構成するには適していない構造である。
4 壁式構造は、柱とはりではなく、壁板により構成する構造である。
答えは 3 なんですが、この問題を2~3回繰り返し解いていくと答えを覚えてしまうんです。
ラーメン、トラス、アーチ、壁式、の組み合わせの問題の不適切はアーチだな、ふむふむ
といった感じで。
答えを覚えているのですから当然正解します。正解はするんですが、それでは知識が増えません。
大事なのはラーメン、トラス、アーチ、壁式の各構造の特徴やメリットを覚えることですから、4択の中のどれが正解かを覚えるだけでは意味がありません。
なので「一問一答形式」での取り組みが大事になってきます。
以下の選択肢は正しいか正しくないか
・ラーメン構造は、柱とはりを組み合わせた直方体で構成する骨組である。
以下の選択肢は正しいか正しくないか
・トラス式構造は、細長い部材を三角形に組み合わせた構成の構造である。
以下の選択肢は正しいか正しくないか
・アーチ式構造は、スポーツ施設のような大空間を構成するには適していない構造である。
以下の選択肢は正しいか正しくないか
・壁式構造は、柱とはりではなく、壁板により構成する構造である。
このように選択肢ごとに正誤を解いてくことで知識が定着していきます。
宅建試験は4択なので、選択肢ごとに正誤を解いていくと普通に過去問を解くよりも単純計算で4倍の時間がかかることになりますが、時間をかけるだけの意味と効果が必ずあります。
分野別に解く
宅建の学習は分野別に行う方が効率がいいです。過去問も同じ分野の問題を一度にまとめて解いた方が知識が定着しやすいです。
過去問道場さんでは分野別・細分別(分野内の細分)に出題できますので活用したいところです。
繰り返し解く
不動産関係資格の著名なYoutube講師の方で「棚田行政書士」という方がいまして、この方が提唱する「紙一枚勉強法」という勉強法があります。
人間の脳は一度覚えたことでも時間経過と共に忘れてしまいます。
忘れかけた頃にまた覚え直すと、前回覚えたときよりも強く記憶にのこります。
また忘れかけた頃に覚え直すと、より強く記憶にのこります。
これを何度か繰り返すことで完全に記憶に定着します。
いわゆる「ポモドーロ・テクニック」と呼ばれるものの応用なんですが、資格の勉強でも同じことを期間をおいて何度も繰り返し学習することで知識を定着させることができるそうです。
以下の画像はワタシが宅建の勉強中に残した記録です。

「一度覚えたらそれでお終い」とはせずに、期間を置いて何度も繰り返し覚えることで知識を定着させることができるようになります。
参考までに日ごとの学習データも掲載しておきます。


過去問学習は効率的に
過去問はあくまで学習方法のウチの1つですが過去の実際の試験で出題された問題ですので、繰り返し何度も解くことで出題の傾向や重要論点が自然と身につきます。
片っ端から過去問を解いていくだけでは過去問学習の効率は上がりません。効率よく学習することで過去問だけでも合格点は取れるはずです。ワタシも過去問学習しかしませんでしたし。
まとめ
文中でも書きましたが、解答用紙の右半分、宅建業法と5問免除科目を全て正解できれば、左半分の民法や法令上の制限、税その他の科目で10点取れば合格ラインの40点が取れます。
解答用紙の左半分を全問正解しろ!と言われたら尻込みしてしまいますが、右半分なら決して無理なチャレンジではありません。
多くの受験者や宅建講師が口を揃える、「宅建業法は完璧にして得点源とする」ことができれば合格は十分見えてくると思います。















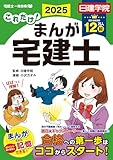









 (わかって合格(うか)る宅建士シリーズ)](https://m.media-amazon.com/images/I/51c4om0F-HL._SL500_.jpg)